こんにちは。
お子さんのこんな様子に、心当たりはありませんか?
- 「やめて」と言っても止まらない
- じっとしていられない
- 緊張しやすくて、ストレスに弱い
- 集中力が続かない
- 滑舌が悪い
- 食べ物の好き嫌いが多い
「なんで言っても直らないんだろう…?」
そんなふうに感じているママ・パパへ。
実はこれらの行動、“原始反射”が残っていることが関係しているかもしれません。
■ 原始反射ってなに?
赤ちゃんって、生まれた時から“本能的な動き”を持っているのをご存じですか?
たとえば──
🔸モロー反射:大きな音にビクッとして、手を広げてしがみつこうとする動き
🔸把握反射:手に触れたものをギュッと握りしめる動き
これらは成長とともに自然に消えていくものですが、3歳を過ぎても残っていると、行動面や学習面に影響を及ぼすことがあるんです。
原始反射は脳のなかでも脳幹という部分がかかわっています。
脳幹は脳の中でも土台となる部分です。「ちゃんとしなさい」や「静かにしなさい」という言葉は、いわば大脳に対する言葉で、大脳は土台である脳幹の上に成り立っています。脳幹がしっかりしていないと、どんなに注意したとしても、なかなか聞き入れてもらえません。
今回のブログでは、特に日常生活に影響しやすい3つの反射をご紹介します。
もし当てはまる行動があったら、少しずつ“遊び”の中で取り入れられる簡単な対策も紹介しますね。
① モロー反射(ビクッと驚く)
これは先ほども出てきた、大きな音やまぶしい光に対して、赤ちゃんがビクッと手足を広げる反射。
これは本来、生存本能からくる動きですが、成長後に残っていると…
● よく見られる特徴
- 車酔いしやすい
- 音に敏感(聴覚過敏)
- 周辺視野に映るものに注意がそれる
- 白い紙の文字が読みづらい(光過敏)
● 対策:ひとで体操
“ひとで”のように両手両足を大きく開いて→ぎゅ〜っと縮こまる。
この繰り返しの動きで、神経系が落ち着きやすくなります。
寝る前のリラックスタイムに、親子でやってみてください♪
② 把握反射(何でも握っちゃう)
赤ちゃんの手に指を乗せるとギュッと握ってくれる、あの可愛らしい反応。
でもこの反射が残っていると、日常生活でいろんな困りごとが出てきます。
● よく見られる特徴
- 筆圧が強すぎる/弱すぎる
- 手先が不器用でクレヨンやお箸を持ちたがらない
- キャッチボールなど球技が苦手
● 対策:とことん「握る」遊びを
スライム、粘土、新聞ビリビリ、タオルをねじねじ…。
「握る・ちぎる・丸める」など、指や手のひらをたくさん使う遊びで自然と改善されていきます。
おうちでも簡単に取り入れられますよ!
③ 緊張性迷路反射(スーパーマン反射)
聞き慣れないかもしれませんが、この反射は「頭を上下に動かしたときの全身の反応」です。
頭を下にすると丸まる。
頭を上げると手足がピンと伸びる──まるでスーパーマンが飛んでるような動きです。
この反射が残っていると…
● よく見られる特徴
- 姿勢が崩れやすい(下を向くと猫背に)
- 空間認知が苦手(似た形の文字が見分けづらい)
- 乗り物酔いしやすい
- 水泳(特に平泳ぎやクロールの息継ぎ)が苦手
たとえば、b・d・p・qやm・wの区別がつかず、読み書きに困ることも。
場合によっては「ディスレクシア(読み書き障害)」と診断されることもあります。
● 対策:あそびの中で頭をたくさん動かそう
「頭を下げる」「上げる」動きがたっぷり入った遊びが効果的!
- サッカー(ボールを見る→周囲を見る)
- 四つん這いで歩く“クマ歩き”
- トンネルくぐりや高低差のある遊具もおすすめ
子どもにとっては“運動”というより“遊び”の延長なので、ストレスなく取り組めます♪
まとめ:まずは「遊び」から始めよう!
今回ご紹介した3つの原始反射以外にも、
・脊椎ガラント反射
・ラビン反射
・ATNR(非対称性緊張性頸反射)
など、いろんな種類があります。
でも共通して言えるのは、
**「残っている反射は、体をしっかり使って“使い切る”ことで自然と消えていく」**ということ。
最近はタブレットやスマホの時間が増えて、
体をたっぷり動かすチャンスが減っている子も多いですよね。
「遊びの中で、体を思いっきり動かす」
これが、原始反射とうまく付き合っていく一番の近道です。
☘ さいごに…
もし今回の内容で「うちの子にちょっと当てはまるかも…?」と思ったら、
ぜひ一緒に公園に行ったり、簡単な動き遊びを取り入れてみてください。
無理せず、楽しみながらがいちばん大切です😊
「子どもって、ちゃんと理由があって動いてるんだな」と思えたら、
きっと、ちょっとだけ育児がラクになりますよ。









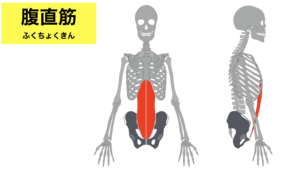
コメント